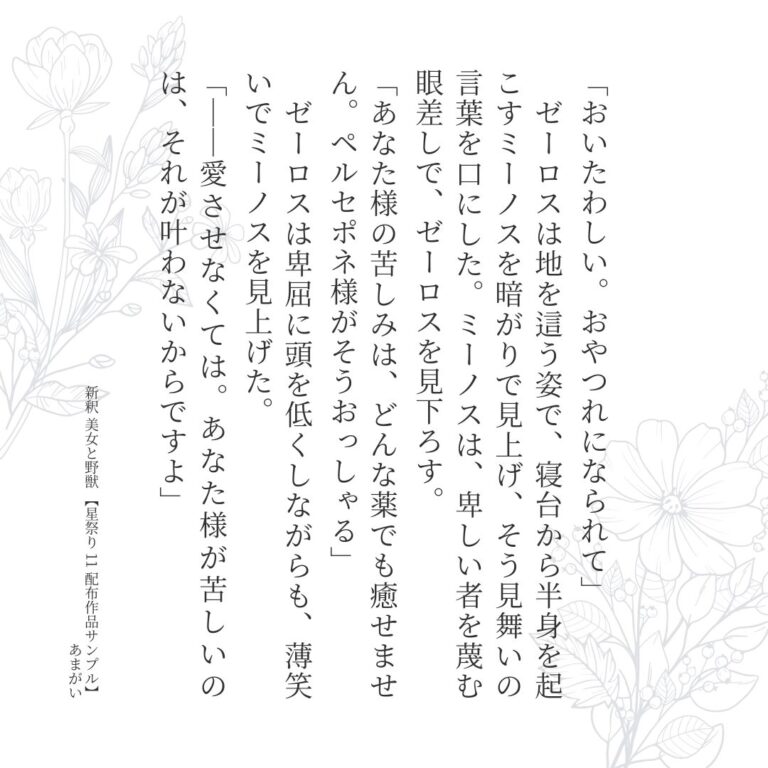新釈 美女と野獣
Summary
✦ 聖戦後冥界、トロメア宮。敗戦したミーノスは、原因不明の激痛に襲われ続ける。
✦ 裁判官の職 務も放棄せざるを得ない重態。
✦ 原因はミーノスと相打ちになったアルバフィカだと冥妃ペルセポネはミーノスに告げる。
✦ 「アルバフィカの愛を得ることが、その激痛から逃れる唯一の方法」
✦ ミーノスは第八獄コキュートスに捕らえていたアルバフィカを、トロメア宮に召し出す。
✦「美女と野獣」をモチーフに、ミーノスとアルバフィカで再解釈した物語。
✦ The Rose and the Judge: A Retelling of “Beauty and the Beast”— Japanese Original Text
新釈 美女と野獣
✦ ✦ ✦
胸が灼けつく。
頭が割れるように痛む。
ミーノスはそう言って、トロメア宮から出て来なくなった。
あれもひとつの戦争後遺症なのか──と、副官のルネは、上官ミーノスのいない第一獄、裁きの館で吐息した。
冥王ハーデスと戦女神アテナの聖戦が終わった。しかし冥王が封印されたところで、冥界が消滅するわけではない。地獄の獄卒である冥闘士等は、次に決着の持ち越された聖戦の後も、冥府で死者の魂を裁き、罰をつかさどっていた。
冥府に閉じ込められているという点では、冥闘士も死者と変わりはしない。しかしその権能は冥界において受肉した人のようなもの。霊魂である死者とは、持てる力も振るえる権勢も、格段の違いがある。
死者に対する圧倒的優位を保ちながら、冥界の統治は続けられていた。
だから、法廷の裁判官であるミーノスも、冥界から期待されているのはその役目の遂行である。
それにもかかわらず、ミーノスは心身の不具合を理由に、職務の放棄を続けていた。
聖戦が終わって一年、封印されようとも冥界に冥王の加護は及ぶ。108の冥闘士は冥界において聖戦の傷を癒している頃だった。しかしルネは、処置がない、と、判断していた。あれは戦傷ではない、と、だいぶ前に理解していた。
✦
──なぜ、負けた。
──なぜ。
日毎夜毎、胸を掻きむしる苦痛にさいなまれ、ミーノスは暗闇の中で呻いていた。
冥闘士の頭の一角である天貴星グリフォンが、苦悶の声を漏らすなど、恥辱そのものである。しかし耐え難い。それでも、額にいくつも汗を浮かばせ、掛布を引き裂く強さで握り締めながら、来客だと知らされると平静を装った。
来客は地奇星フログのゼーロスで、冥妃ペルセポネの使いだと言う。面通ししないわけにはいかなかった。
「おいたわしい。おやつれになられて」
ゼーロスは地を這う姿で、寝台から半身を起こすミーノスを暗がりで見上げ、そう見舞いの言葉を口にした。ミーノスは、卑しい者を蔑む眼差しで、ゼーロスを見下ろす。
「あなた様の苦しみは、どんな薬でも癒せません。ペルセポネ様がそうおっしゃる」
ゼーロスは卑屈に頭を低くしながらも、薄笑いでミーノスを見上げた。
「──愛させなくては。あなた様が苦しいのは、それが叶わないからですよ」
その言葉に、ミーノスは頭に血をのぼらせた。それが一層、痛みとしてミーノスをさいなむ。それでもミーノスは怒りを抱いたままゼーロスに言葉を返した。
「貴様、私を愚弄するのか。いかに冥妃のお言葉でも、おまえのことは許さぬぞ」
ゼーロスは笑った。おゆるしくださいませ、と、恭しく言いながら。
冥妃はグリフォンの長い不調に心を痛めている。早く回復してほしい。そのために、ミーノスの苦しみの根源をそちらに送る。愛させれば、癒される。冥王ハーデスが、そうであったように。──そうペルセポネはゼーロスを介して伝言した。
かくして、トロメア宮にはその翌朝。薔薇園に舞い降りた朝露のように、第八獄の氷地獄で捕らえられていた霊魂がひとつ、生前の人の姿を与えられてやって来た。
アルバフィカだった。
戦女神の聖域の魚座の黄金聖闘士。そして、聖戦の緒戦で、その毒薔薇と猛毒の血で、ミーノスを倒した。そして自身もまた、滅んだ。
アルバフィカは、静寂の中に怒りを秘め、卑劣を蔑む冷めた眼差しで、トロメア宮の中庭にいた。そこへ置き去られたのだ。
生前の黄金聖闘士としての力も、血の猛毒も、冥界を害するものは消し去られ、無力なひとりとしてそこにいた。
「ミーノス。おまえはこれほど私が憎いか。──恨んでいるのか。我が師父ルゴニスの霊魂に、氷地獄よりもなお苛烈な罰を与えると言った。それを免れたいなら、身代わりに私にここへ行けと」
高い空に響く声は、ミーノスの鼓膜にあの日のことを思い出させた。聖域の間際の場所で、冥王軍の進撃をたった一人で迎え撃つべく、佇んでいたアルバフィカ。
──なぜ、負けた。
──緒戦で。なんの戦果も、挙げることもなく。
トロメア宮の中庭には、かねてから薔薇があった。薔薇だからと、特段気に留めたこともない。しかしいまは、それがアルバフィカと呼応するように、ひとつの景色をつくっている。
ミーノスの頭は、ふたたび激しい痛みを覚えた。しかしそれを気取られぬように、拳をきつく握り締め、目の前のアルバフィカを昏い目で見据えた。
アルバフィカは言う。
「私はおまえの仇か。おまえを討った咎で、貴様等は我等に責苦を与えたいのか。よかろう。苦痛も屈辱も、何ほどのものでもない」
ミーノスはアルバフィカの首を見つめた。痩せた細い、白い首。手を掛ければ、挫くのに瞬きほどの時間もかからない。それでこの苦痛は終わると、ミーノスは思った。
しかし、あの時のように──自らの見えない糸で、アルバフィカの全身の骨を砕き、吹き出すおびただしい血の海に倒した──蒼白なアルバフィカの顔を、また見たいとも、思わない。
ミーノスは、アルバフィカに背を向けると、密かに胸を押さえた。
「きみはなんとも、健やかなことだ」
そう言い置いて、去った。
✦
アルバフィカは、偽の日がのぼり、偽の星空が広がる冥界のトロメア宮で、薔薇の世話をして最初の一日を過ごした。なんの労役も、刑罰も、あるわけでもない。ミーノスはほとんど姿を現さず、ただ夕食に、長いテーブルの先に座りに来る。
「なんなんだ」
夜、アルバフィカは食堂のテーブルの端から、向こう岸のミーノスにそう呼び掛けた。
「おまえはなんのために、私をここへ呼んだ」
アルバフィカの問いに、少し間を置いて、ミーノスは答えた。
「賭けをしませんか」
「なんだと」
「あとひと月の間に、きみが私を愛せたら、きみの好きにするといい」
アルバフィカは、聞き違いかと耳を疑う顔をする。ミーノスは続けた。
「それができなかったら、死になさい。ただの霊魂に戻るだけでなく、霊魂さえも永久に、消滅してしまうといい」
アルバフィカは顔を歪めた。あらんかぎりの侮蔑を込めて。
「おまえは頭がおかしいのか? 侮辱にもほどがある。どこの誰が、そんな条件を突きつけられて、その相手を愛するというのか」
しかしミーノスは、事もなげに言った。
「それが叶わないなら、私も同じように、消えてなくなりますから」
アルバフィカは再び、呆気に取られた顔をする。そしていぶかしげに言った。
「……おまえまさか──、おまえこそが、罰せられているのか。私に敗れた、咎で。それはよこしまな冥府の神の、おまえへの罰なのか?」
それを聞くと、ミーノスは声をあげて笑う。
「──もう、とうに。罰を受けていますよ。それがハーデス様からではないというだけで」
ミーノスはテーブルに両肘を付き、両手を絡ませて顎を預けた。
「聖戦できみに敗れ、冥界に封じられて以降、もう長らく、頭と胸が──心臓が、痛みます。もう耐えられない。このままではいずれ発狂するでしょう。その前に、この痛みが取り除かれることがないなら、消えても構わない」
「なんという、身勝手な」
アルバフィカは言葉を失い、食事も半ばにして席を立った。
部屋に戻ってからも、アルバフィカはミーノスの言葉を思い出して苛立った。
愛の告白とは到底受け止められない脅迫。しかし、何が目的なのかもわかりかねた。
理解不能の取引。
ただ振り回され続けるだけである。
しかしアルバフィカは思った。ミーノスはひと月と言ったのだ。ひと月過ぎて、先ほどの言葉の通り、アルバフィカがミーノスを愛することがなければ、魂までも討たれて終わる──それだけのことだと。
アルバフィカは氷地獄に残してきた師父ルゴニスを思った。地獄に違いないが、そこには同じく冥王への反逆罪とされた歴代の聖闘士も封じられている。そして密かに戦女神からの加護も送られ、罰は和らいでいるのだ。
恩義ある師父の眠りさえ安らかならば、自分はどうなっても構わない。そう、アルバフィカは思った。
翌朝、中庭の薔薇園に出掛けたアルバフィカは、世話を終えると、漉き紙と黒鉛で花の素描を始めた。与えられた部屋の机の引き出しで見つけた、絵を描くのに使える道具だった。
夕食のときに、やはりテーブルの向かいに現れたミーノスに、「今朝は、なにをしていたのですか」と尋ねられる。
絵を描いていた、と、答えると、ミーノスは「絵が好きなのですか」と問うて来る。
アルバフィカはばつの悪い顔をした。
「初めて描いた。得意ではない。ただ、やってみたいと思っていた。部屋に道具があったから」
あとひと月で、消えてなくなるのだから、という言葉を、アルバフィカは飲み込む。
「ほかに欲しいものは?」
唐突なミーノスの問いに、それでも「ない」と、アルバフィカは答えた。それでミーノスは黙り込み、その夜の会話は終わった。
アルバフィカが部屋に戻ると、中央の円卓に、チョークや木炭、キャンバスや油彩の道具が所狭しと並べられていた。木製の三本足のイーゼルまで置かれていた。
きみが私を愛せたら──、というミーノスの言葉が頭によみがえる。
愛する、とは、どういうことだろう、と、アルバフィカは画材を前に、沈黙した。
翌日、アルバフィカはさっそく風景画を描きに、イーゼルを中庭へ持ち出した。道具を見ていると、使ってみたくなったのだ。昨日の薔薇を改めて素描し、昨日より形が気に入ったので、また何枚か描く。そしてこの薔薇の花壇を描いて、油彩で仕上げようと思い立ったのだ。結局、陽が暮れて薔薇が見えなくなるまで、アルバフィカの作画は続いた。
「随分長い時間、絵を描いていましたね」
夕食で、またミーノスにそう言われる。姿を現しはしないが、この男は、ずっと自分を見ているのだと、アルバフィカは理解した。
日に日に、アルバフィカはさまざまな被写体を描くようになった。薔薇の花に慣れたら、次は芍薬、そしてデルフィニウムを描いた。ライラック、若葉の美しい楓、外庭にあるマロニエ並木。キャンバスの画角は少しずつ広がって行く。
日没の頃、アルバフィカが一日の作画を終え、道具を持って部屋へ帰る道行──ミーノスに会った。食堂以外で顔を合わせるのは、最初の日以来だった。回廊に立つミーノスは、もうひとつの小さな中庭に向かっている。近づくと、白い円柱の影から、イーゼルが見えた。彼もまた、筆を取って油彩をしていたのだ。
アルバフィカはつい、声を掛けた。
「何を描いているんだ」
ミーノスは声の方を振り向く。そして「噴水を」と答えた。
駆け寄ったアルバフィカはキャンバスを覗き込み、その瞬間、声を失った。驚くほどに、油彩の出来がよかったのだ。キャンバスの中に、小さな噴水庭園が造り出されたように、その絵は精巧だった。アルバフィカは密かに足を震わせた。この半月、だいぶ絵に打ち込んで来たつもりで、日に日に上達している実感があった。だいぶ描けるようになったと満足していた。だというのに、目の前には遥かに優れた作画があったのだ。
「おまえ、絵を描いていたのか」
アルバフィカがそう問うと、ミーノスは答えた。「いいえ」と。そして続ける。
「最初は、きみの真似をしてみただけでした。けれど描くうちに、こうしていると、頭の痛みが薄れて行くとわかったので」
アルバフィカは絶句した。ほとんど同じ頃に絵を描き始めたと知り、悔しさのようなものが込み上げたのだ。
「おまえは変わっている。絵で頭の痛みがなくなるなんて。──私は、頭を悩ませてばかりだ。それが苦しいわけではないが」
つい、口をついたアルバフィカのその言葉に、ミーノスは言う。
「胸の焼けるような痛みは変わりません。けれど、いま、少し薄らいだ」
アルバフィカが、問うようにミーノスに視線を向けると、ミーノスは続けた。
「きみが現れたから」
「どうやったら、こんなふうに描けるんだ…」
夕食を終えて、アルバフィカは自分の部屋に持ち込まれたミーノスの油彩を、次々と手にとっては睨むように眺め、ため息をついた。
「さあ。見たままを描いただけなので」
ひとりごとだったのに、応答してくるミーノスに、アルバフィカはなにやら腹が立った。しかも写し取ったように描いた絵を「見たまま」と軽く言う。それにどれだけ骨を折っているかを振り返ると、どうしてもアルバフィカは苛々としてしまった。
「しかし、きみの絵はおもしろいですね」
ミーノスも、テーブルに置かれたアルバフィカの絵を手に取る。
「本物よりも、本物のようではありませんか。私の絵とは違う」
「そうか?」
つい上機嫌に、アルバフィカは答えてしまった。この男は見る目があるようだと、思ったのだった。
「明日はなにを描くのですか」
しかし講評はすぐに終わってしまった。アルバフィカはしぶしぶと「本当はそろそろ人物画を描きたいのだが」と話を合わせた。
「ここにはおまえ以外に、人間はいないのか?」
「いません」
「おまえ、絵の被写体というわけにもいかないだろう」
「構いませんよ」
ミーノスは平然と応じた。そして言う。「私もきみを描いてみたい」と。
しかしアルバフィカは首を振った。
「私はそんなに長い時間、ただ座っていられない。──もう、あと半月だ。残された時間で、自分がどれだけ上達できるのか、試したい。わずかな時間も惜しい」
「では、私は昼間、絵を描いているきみを見て、きみを描きましょう」
ミーノスはそう言った。そして笑う。
「そう、もっと早くそうすればよかったのです。それなら、頭も胸も、あまり痛まなくなるかもしれません」
ほんとうにおかしな男だと、アルバフィカはつくづく思った。そしてミーノスは少し黙り込んだあと、呟いた。
「私は、どうすれば愛されるのでしょうね。どうすれば嫌われるかは、よくわかるのですが」
「──知るか」
アルバフィカは話を切り、「そこへ座れ」とテーブルのそばの肘掛け椅子を指差した。すぐにイーゼルを引き寄せて、広げる。
「被写体になると言ったな。今夜から、なれ。──そうだ、頭と胸が痛むと言ったな。楽な姿勢で構わないぞ。言ってくれ」
そして夜更けのその先の、ほとんど力が尽きるまで、アルバフィカはミーノスの肖像画を描き続けた。
✦
日の出から、日没まで、日の光が風景を照らす間、アルバフィカは中庭の風景を描き続けた。ゴシック建築の意匠を持つ、前時代的でありながら古典的荘厳を体現したトロメア宮の外観も、キャンバスに含めるようになった。
日が落ちると、夕食も手早く済ませ、シャンデリアの明るい自分の部屋で、ミーノスの肖像画の続きを描いた。
死者として冥界で与えられた身体も、地上のものと同じように疲労し睡眠を欲するのだと実感し、アルバフィカはその煩わしさに舌打ちしたいほどだった。
そして、疲労が募っているからだと、繰り返しアルバフィカは自分に言い聞かせなくてはならなかった。──錯覚するのだ。目の前のミーノスを描き取り、手元のキャンバスに描き出すうちに、これはあの冷淡で傲慢な冥界三巨頭のグリフォンなのかと、強い違和を覚えるようになった。
生前の、聖域を目前とする場所で出会ったミーノスは、冥王軍の名にふさわしい魔物だった。酷薄な笑みと弱い者たちへの無情な暴力。まるで死が救済であるかのように、この世の生を刈り取らんとする。
これはあの、魔物なのだろうか──アルバフィカは、キャンバスの中のミーノスをたびたび見つめた。自分が一体なにを描き出しているのか、自分でもわからない。しかし、これはなんら偽りではないとも、わかっている。認めないわけには、いかないのだった。
──きみの絵は、本物よりも本物のようではありませんか。ミーノスの言葉が、よみがえった。
✦
そんな、夜の更けた頃だった。
先触れがけたたましい蹄の音を立て、馬をかってトロメア宮に駆け込んだのだ。
第八獄の氷地獄において、アルバフィカの師父ルゴニスの霊魂に異変が起きているという報せだった。個々の霊魂を消滅させ冥界から無へと還すほどではなく、消滅させずに刑を課し続ける──それが冥界の在り方だった。
その中で、ルゴニスの霊魂だけが弱り続けているという。
先触れの論点は「冥界を陥れるための、聖闘士側のたくらみではないか」というものだった。しかしアルバフィカは師父の名に聞き耳を立て、すぐに理解した。
──師は女神の加護を拒んでいる。と。
師に何も知らせずにアルバフィカは決断していた。おそらく師は、それを知ったのだろう。そして師は、身代わりになったアルバフィカの身を案じ、自分を責めている。
アルバフィカはミーノスに訴えた。
「私を、第八獄へ戻してくれ。師に伝える。私が選んだことだと。私がどうなろうと、師に責はないのだ。まして私が、おまえを愛することもない。そしておまえも消えてなくなる。それで、我らになんの不利益が? もともと私はおまえと、差し違えたのだから」
ミーノスは答えた。
「約束の日まであと8日。その日までに、戻って来るのなら」
「ああ、戻るとも。この絵も途中なのだから。──ああ、師が。重罰を免れたというのに……!」
アルバフィカはその夜の内に、トロメア宮の馬車で第八獄に向かった。
第八獄の氷地獄は、いつもより数の多い見張りの冥闘士に囲まれていた。アルバフィカは馬車を降り、氷地獄の氷原へ駆けた。
師を呼ぶ。
「ルゴニス先生! アルバフィカは無事です。どうか、どうか御身を──」
これが冥界においても消滅することかと実感するほど、ルゴニスの霊魂は弱っていた。
アルバフィカは、師父のそばを離れられなかった。
日は瞬く間に過ぎてしまう。気が付けば、約束の8日は一昨日のことだった。
アルバフィカは、回復した師父に、トロメア宮へ戻ることを伝えた。
「なぜ戻る」
ルゴニスの問いにアルバフィカは答えた。
「あの男に伝えなくては。私の見た、あの男を」
「グリフォンの、不当な拘束ではないか」
「先生。私はなんと心無い。言えなかったのです、あなたに。私は、トロメアに戻りたい。それが私の本当の心なのに。──彼は、私の絵をわかってくれます。それが、私には……」
アルバフィカの答えに、ルゴニスはもう問答をしなかった。「行くがいい」と、言った。
アルバフィカが氷地獄の同胞たちに見送られ、再び馬車でトロメア宮に帰還したときだった。トロメア宮は、廃墟のような荒廃を見せていた。遠い昔に滅びたような。ひと気のなさと、夜の時間帯の暗さが、尖塔を持つトロメアの姿を一層怪奇的に見せた。
アルバフィカは馬車を降りると、中庭に向かい、ミーノスの名を呼んだ。
誰も答えない夜空の下、アルバフィカはトロメア宮を駆けた。ミーノスを探した。
あまりこの城の中を探ったことのないアルバフィカには、自分の部屋と食堂しかわからない。まさか自分の部屋にはいないと思ったものの、立ち寄る。カーテンが開いたまま、灯りの消えた部屋に月の光が差し込んでいる。中央の円テーブルの上には、キャンバスが置かれていた。
近寄って、アルバフィカは、置かれたキャンバスを手に取る。それを目にしたとき、アルバフィカは息を飲んだ。
それは紛れもなく、アルバフィカの肖像画だった。
目を細め、うつむいた優しげな微笑が、視線の先を見つめている。自分の肖像画ながら、アルバフィカは、美しい…、と知らず知らずに感嘆していた。視線の先にあるものは、背景のトロメア宮の造形からするとおそらくは薔薇園である。
まるでこの世の、何もかもを受け入れるような、愛に満ちた微笑。あるがままのこの世界を。
(私は、こんなふうに世界を、すべてを、見つめることができていたのだろうか)
アルバフィカは、涙が溢れて来るのを止められなかった。これはミーノスが、アルバフィカをそのように見ていたということだったから。
──私は、どうすれば愛されるのでしょうね。という、ミーノスの言葉が、アルバフィカの耳によみがえる。
違う。アルバフィカは思った。
もう、愛されていた、と。目の前の肖像画が間違いなくアルバフィカなら、ここに描かれた人物は、なにもかもを等しく愛している。ただその愛は、ミーノスひとりに注がれることがないだけなのだ。
アルバフィカは涙を拭った。万が一にも先に見られたくなくて、アルバフィカは完成間近だったミーノスの肖像画を、衣装箱の奥に隠していた。肖像画を手に取り、アルバフィカは部屋を出た。ミーノスを探しに。
✦
──なぜ、負けた。
──なぜ。
いつもの問い掛けが、責苦そのものとしてミーノスに襲いかかる。
誰もいないトロメア宮で、もはや誰にはばかることなくうめき声を上げ、ミーノスは胸を抑えて倒れ込んだ。
心臓を焼き尽くすような痛みが、時を追うごとに、苛烈に体をさいなむ。
──なぜ?
──あの美しさに、心を奪われたから。
ミーノスはもう理解していた。聖域で、一度はアルバフィカを死の淵へ追い込んだ。殺したと思った。それで終わりだと。しかし、彼が生きていたと知って、そして自分を追って村の破壊を止めに来たと知って──確かに歓喜した。彼がまだ生きていたことに。
だから、聖闘士への侮辱へかこつけて、言ってしまったのだ──見逃して差し上げます、と。
そのときにはもう、負けは決まっていた。
ミーノスは、アルバフィカがこの世に存在することを受け入れていた。その美しさが、自分にとって快であると自覚したときに。そして、その美しさとは、魔物さえ生ある者として肯定する眼差しによって、快なのだとわかったときに。
アルバフィカの肖像を描き、敗戦の理由を理解したときに、燃え盛る憎悪としてミーノスを苦しめていた頭痛は、消え失せた。
しかし焼ける心臓の痛みが消えない。
ミーノスは石の床に、のたうってもがいた。
アルバフィカは戻らない。8日目にも戻りはしなかった。和らいでいた激痛は、その夜から、再び猛威となってミーノスを苦しめた。心臓を焼いた。最後のアルバフィカの猛毒の血が、ミーノスを死に至らしめたときのように。
自刃を、ミーノスは思い立った。
アルバフィカは戻らない。痛みは増すばかり。ここに止まる理由は、もうなにもなかった。
「ミーノス!」
幻のように、アルバフィカの声が響いた。
ミーノスは、すでに苦痛を訴える力も残っていない。ほんのわずかに、声のした方の指を動かした。
「ミーノス、戻ったぞ! 遅れて、すまなかった」
息を上げ、掠れた声のアルバフィカがそう叫んだ。そして、噴水の見える小さな中庭を臨む回廊に横たわる、ミーノスのそばに寄った。膝を付き、ミーノスの手を取る。
「ああ、私のせいだ。私が約束をやぶった…」
アルバフィカは、はらはらと涙をこぼした。そして、冷え切ったミーノスの手を頬に当てる。春のような体温が指先に伝わった。
「ミーノス。おまえは、私の絵の理解者なだけではない。私の、理解者だ。私は、おまえを、──愛している」
アルバフィカは、膝のそばに置いたミーノスの肖像を思い返した。
まるで──まるで泣いている子供。ただ一人で。
夜が明け始めると、トロメア宮は息を吹き返したようだった。朝焼けに包まれ、金色に染まった尖塔が夜の闇を脱ぎ捨てて行く。
十分に明るくなった頃、中庭に出たミーノスとアルバフィカの二人は、並んでイーゼルを立てた。朝日に照らされる薔薇を、描き取るために。
(了)
✦End notes✦
お読みくださり、ありがとうございました。
AO3 Translation : 📎 English | 📎 French
二次創作(小説・イラスト):📎Pixiv
各種 SNS / まとめリンク:lit.link/amagaishuka